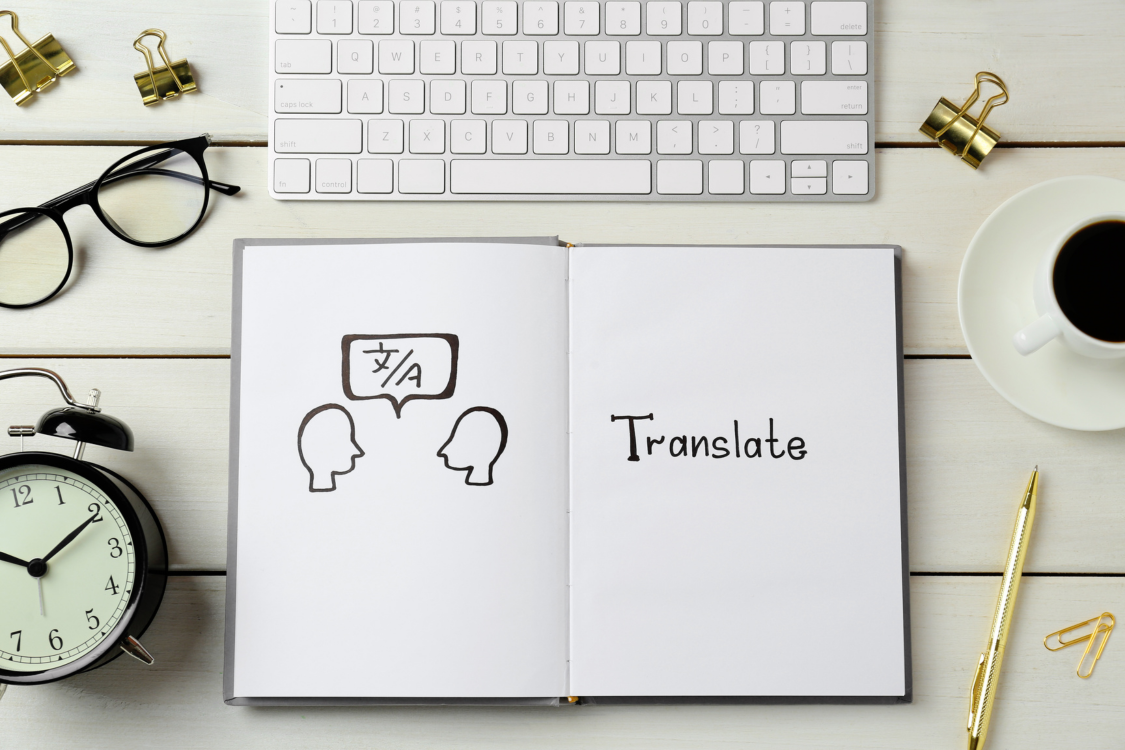雑貨業界、小さな会社の海外チャレンジ 海外市場でのネーミングの注意点とは?
日本へのインバウンド需要が高まる中、自社商品を海外に展開したい、販売したいと考える事業者が年々増えています。今回は海外市場への展開を視野に入れた社名、ブランド名、商品名などの「ネーミング」について、中小企業の視点から考えていきます。

日本企業の海外展開におけるネーミングの課題
まず、会社を設立する際にどんな会社名にするか、事業を受け継いだ時に代々続いている会社名をどうするか、新しいブランドを立ち上げたり新しい製品を開発したりのネーミングをどうするか、皆さんネーミングで悩むことが多いと思います。
「これだ!」と思った名前が、国内ですでに同業他社に使われていたり、ドメインが取得できなかったり、商標登録されていたりすることはよくある話です。似たような名前が多いと混同されやすくなることもあります。
さらに、海外展開を考える場合、次のような課題が加わります:
- 他社との混同リスク:海外市場にも同じような名前が存在する可能性があります。
- 発音のしやすさ:英語圏では発音しにくい日本語の名前が少なくありません。
- 意味の適切さ:英語表記にしたときや発音で、誤解を招く意味にならないか注意が必要です。
会社名、ブランド名、商品名、自分たちが気に入って納得して、憶えてもらいやすい、かつドメインも獲得できる新しい名前をつけることは世界中で困難になってきています。
では、これから海外に自社ブランドや商品を展開したい、と考えている中小の事業者さんに、海外に展開する際のネーミングにまつわる注意点を事例を使ってみてみましょう。
創業者名を社名に使う場合の利点と注意点
中小企業のみならず、特に、昭和(もしくはそれ以前)の創業で、ものづくりに関わる多くの企業の社名は、創設者の名字であることや、もしくは日本の伝統的な響きのある社名を持つ企業が多いです。代々、長年親しまれた社名で、特に創業者家族が継承している場合、その名前を変更するというのは容易ではないですし、たやすく変えたくないと思うのが信条です。
大企業の例にはなりますが、創業者の名字がそのままブランド名となっている、Toyota、Hondaなどは発音もしやすく、覚えやすく、世界中で知られるブランドになっています。
ただし、創業者の名字が社名やブランド名に使用されている場合、漢字が違っていても読み方が同じ、もしくは似たような名前で商品やサービスが存在している場合もあります。どの企業やサービスか混乱されたり、かつドメインや商標を既に取られていることも多々あります。
- 同名・類似の名前が多い場合:ブランドの混同を招くリスクがあります。
- 発音しづらい場合:英語表記で外国人にとって覚えにくい名前になる可能性があります。
創業者の名前が社名に使われている場合、ユニークな名字で、ローマ字(英語)表記にした際に、日本人以外の人が読みやすく発音しやすいのであれば、そのまま社名やブランド名として残すことは良いと思います。ただし、言うまでもなく、その名前が同業者や他で使用されていない、ということが条件です。
一方で、同じ名字が沢山存在している社名やブランド名、英語表記でグローバル市場で発音がしにくい場合、海外展開を機に社名そのものは変えなくても、ブランド名を変えたり、海外展開用のブランドを新たに作って、そのブランド名で海外展開するのが望ましいでしょう。
創業者の名字で創業した企業が、海外市場での認知度向上のため社名を変更した企業は少なくありません。大手企業でも、グローバル市場での認知度向上や事業領域の多角化を見据えて、企業が社名変更を行うことはよくニュースにも取り上げられています。誰もが知っている日本の有名企業での例を挙げますと、松下幸之助が創業した松下電器産業株式会社は、2008年、パナソニックブランドで海外での認知度が高いパナソニック株式会社に社名変更、全世界でPanasonicで統一しています。樫尾4兄弟が設立した樫尾計算機のカシオも、社名をローマ字のKashioではなく、CASIOにしたことも、世界市場を見据えてあえて変更したことは有名です。

もともとの社名が創業者の名字ではない場合でも、海外市場で認知向上のため社名を変更している企業も多々あります。富士重工業株式会社は2017年に社名を自動車のスバルで認知度が高い株式会社SUBARUに変更していますし、日本電産株式会社も2023年、グローバル市場でのブランド認知向上のためニデック株式会社に変更しています。
長年海外に商品を販売している大手メーカー企業でさえも、社名を世界市場での認知向上のために変更することを考えますと、海外展開を考えている中小企業であればなおさら、展開前に社名、ブランド名を海外展開に適しているかをレビューすることをお勧めします。
社名の英語圏での発音と意味のチェック
ここでひとつ、日本人が社名を日本語で読む発音と、英語圏の人たちがローマ字や英語にした際に発音する場合、異なることがあるため注意が必要です。
長年馴染んだ社名やブランド名が、海外展開の際に英語で発音した時にうまく読めなかったり、英語で意味的にふさわしくない言葉を連想させるネーミングになってしまう可能性もゼロではありません。
会社名やブランド名を英語(ローマ字)にした時、英語のネイティブスピーカーがどう発音するか、どう読むか、意味的に大丈夫かを確認しておくことが大切です。
もし発音しにくい、あるいは英語圏で意味がふさわしくない場合は、海外展開をする前に、ブランド名や商品名を英語圏で適切に発音でき、意味的に問題がないネーミングに変更しておくことをお勧めします。
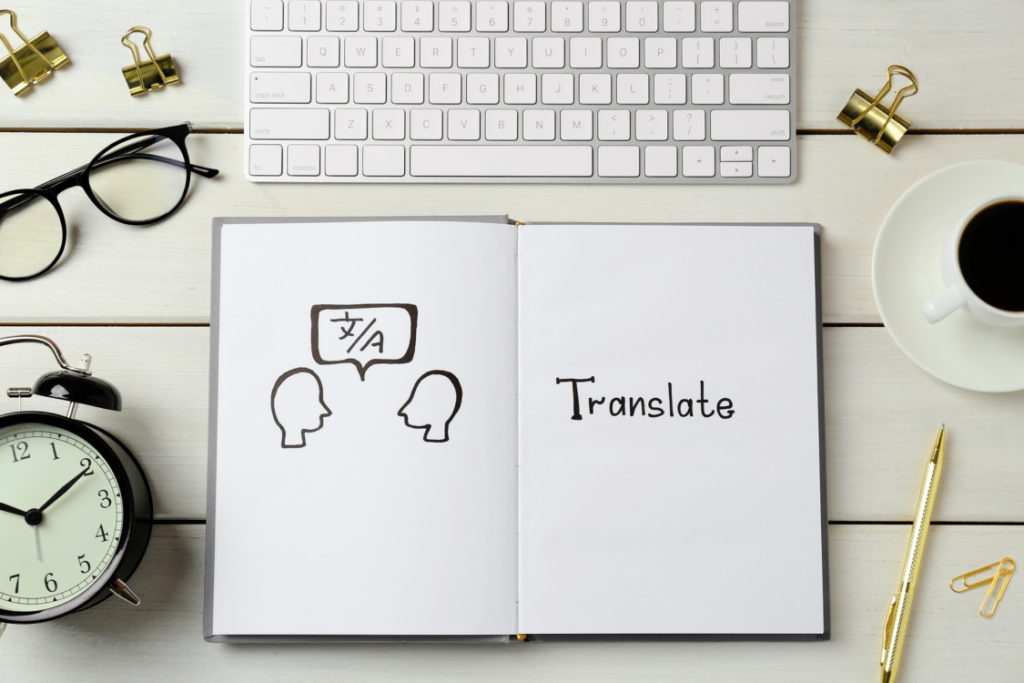
ここでいくつか、アメリカ展開を見据えたネーミングの注意点を挙げます。
日本人には、横文字を一括りに捉える風潮があります。英語なのかドイツ語なのか、フランス語、スペイン語、イタリア語であるかを意識せず、**つづりや響きが「かっこいい」**という理由で横文字を取り入れたブランド名を付ける企業も少なくありません。
しかし、アメリカに展開する場合、もともとの社名やブランド名が英語以外の単語である場合、次の点に注意が必要です:
- アメリカ人にとって発音しにくい
- 読みにくい
- 覚えられにくい
そのため、英語圏で読みやすく、発音しやすいネーミングを心がけることをお勧めします。
また、よく英会話教室で指摘されるように、日本語の「らりるれろ」はすべてRで始まりますが、英語ではLの場合もあります。日本人にとってRとLの発音の違いは聞き分けが難しいため、RやLが含まれるネーミングでは、英語圏で正しく伝わるよう工夫することが重要です。たとえば、RumicaとLumicaでは、日本語ではどちらも「ルミカ」ですが、アメリカでの発音は異なります。そのため、発音に注意が必要です。
さらに、THが含まれる場合も同様です。日本人が「That」を「ザット」と発音するように、日本語と英語で発音が異なるため、英語圏の人がどのように発音するかを確認しておくことが大切です。
もうひとつ、日本では平成ごろから、漢字だけでは読み方が推測しにくい名前を子供の名前に付けたり、日本語ではない海外の言葉を組み合わせた造語を社名やブランド名にすることが流行してきました。漢字の意味と響きがカッコいいとか、綴りからどのように読むのか分かりにくいですが、覚えてもらうということが特徴です。クリエイティブなネーミングとして、日本人はあえてそのような名前の付け方を好む傾向があると思います。漢字にそれぞれの意味がありますので、この漢字を使ってこう読ませるんだ、その意味まで考えると素晴らしいと感銘を受けることもよくあります。
個人的な話を交えますと、私の両親は漢字の意味や画数、見た目、響きを熟考して私に名前を付けてくれました。そのため、この名前には深い愛着があり、大好きな名前です。しかし、名前に使われている漢字が一般的に読みにくいため、初対面の方はほぼ必ず名前を読み間違えます。フリガナがない限り、毎回「この漢字を使ってこう読みます」と訂正することが必要で、これは今でも続いています。

さらに、名前の音だけを知っている方が異なる漢字でメールを書いてくることも少なくありません。訂正するのが面倒になり、異なる漢字や呼ばれ方でも自分のことだと分かれば対応したりスルーしたりしてきました。同じように、漢字から名前の読みが推測されにくい方の苦労をよく耳にします。中には、その経験が原因でアイデンティティの危機を感じる方もいるようです。実際、一生で名前の読み方を訂正する時間を考えたら膨大な時間を費やすことになります。
ニュースによれば、2025年5月26日に施行される改正戸籍法では、戸籍に氏名の読み仮名を記載することが義務付けられ、さらに氏名の読み方は一般に認められているものでなければならないとのことです。キラキラネームの弊害が認知されてきたのだと思います。
話が少し逸れましたが、予算が限られた中小企業にとって、会社名やブランド名が海外展開の際に覚えにくい、あるいは間違ったスペルや発音で覚えられることは命取りになりかねません。
海外展開を見据えた場合、スペルから読み方が想像できにくいネーミングは、スペルそのものも読み方や発音も覚えられにくいため、特にマーケティングに多額の費用をかけられない中小企業にとっては不利に働くことが多い点をお伝えしておきます。
これから海外展開用のネーミングを考える際には、とにかくシンプルさを重視し、スペルから読みやすい、発音しやすい、分かりやすい、覚えやすい名前を心がけてください。

社名とブランド名の一致がもたらすメリット
日本国内では社名とブランド名が異なっていても違和感はありませんが、海外市場では社名=ブランド名がシンプルで覚えやすく、マーケティングの効率を上げる上で重要です。特にアメリカ市場ではバイヤーがその場で即決する傾向が強く、複雑なブランド体系が障害となることがあります。中小雑貨企業が海外展開する場合、会社名とブランド名が同一なのが圧倒的に有利です。
社名とブランド名を一致させるメリット:
- 顧客に覚えてもらいやすい
- マーケティングコストを削減できる
- メッセージの一貫性が保てる
- 顧客の混乱を防げる
- 認知度向上に要する時間と労力を削減できる
日本国内では社名とブランド名が異なっていても違和感はありませんが、海外市場では社名=ブランド名がシンプルで覚えやすく、マーケティングの効率を上げる上で重要です。特にアメリカ市場ではバイヤーがその場で即決する傾向が強く、複雑なブランド体系が障害となることがあります。

大企業であれば、社名とブランド名が異なっていても、多大なマーケティングコストを投じることで、ブランドや商品の認知度を高めることができます。しかし、中小企業では予算が限られているため、**シンプルに「社名=ブランド名」**とすることで、社名(ブランド名)を覚えてもらいやすくすることをお勧めします。
ただし、社名とブランド名を完全に一致させることが難しい場合は、社名の一部をブランド名に活用するなど、顧客に覚えてもらいやすいネーミングを工夫することが大切です。
また、社名の一部をブランド名に使うことができない場合は、海外展開の際に社名を使わず、ブランド名のみを前面に押し出す方法も有効です。そのブランド名を基盤にして、商品ラインを拡充していくことをお勧めします。
最後に、海外展開を見据えて、ネーミングやブランド名を決定する際に最も重要なポイントとして挙げられるのが、海外市場を意識したドメインネームの取得です。
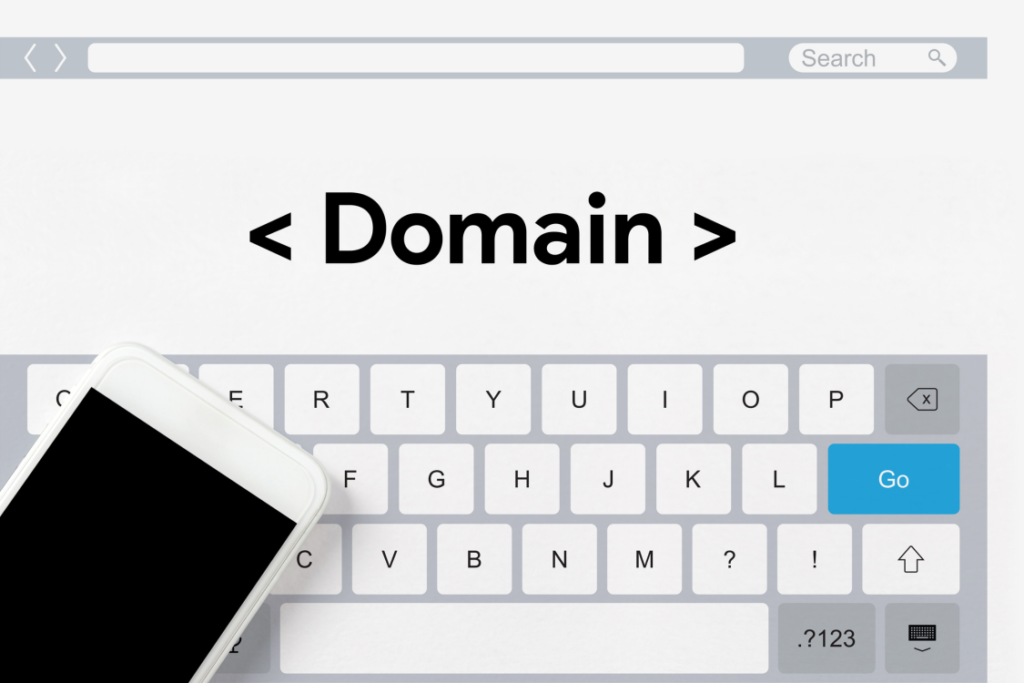
インターネットが普及し始めた当初、日本企業も次々とウェブサイト制作の必要性に迫られ、ドメイン(URL)の取得を進めました。その際、多くの企業が次のような懸念から工夫を加えたドメイン名を採用していました:
- アルファベット表記が長いと覚えにくいのではないか
- 綴りが間違えられやすいのではないか
その結果、会社名の頭文字を組み合わせて**.co.jpや.jp**を付けたり、短縮したドメイン名の間にハイフン(-)を挿入したりする方法が選ばれました。しかし、これらの工夫により、ドメイン名から企業名やブランド名が一目で分かりにくいケースも多く見られました。現在でも、日本企業にはハイフンを含むドメインが多く存在します。
名刺やメールのシグニチャーにURLを記載するため、ドメイン名に会社名を入れる必要はないと考えていた事業者も多かったと思われます。また、似たような社名を持つ企業が多い中で、希望するドメインが既に取得されていたため仕方なく別の形式を選んだというケースも考えられます。
しかし、アメリカ市場への展開を見据えた際には、社名やブランド名を覚えてもらい、認知度を高めるためにも、できる限り社名やブランド名そのままの綴りでドメインを取得することが重要です。
ただし、長年使用してきたドメインを変更するのは難しい場合があります。その場合、企業の公式サイトのドメインはそのままにしておきつつ、商品ラインやブランド名専用にそのままの綴りのドメインを取得することをお勧めします。
仮に希望するドメインが既に取得されている場合は、ブランド名に商品の特徴を追加するなどして、固有性のあるドメインを取得してください。

アメリカ市場でも、シンプルで短いURLの方が覚えやすいため、短くて覚えやすいネーミングでドメインを取得しようと試みるのが一般的です。しかし、.comドメインは既に多くの企業に取得されていることが多く、希望するドメインが取れない場合があります。
そのため、やむを得ず**.netや.usなどの.com以外のドメインを取得する企業も少なくありません。しかし、こうしたドメインを取得した企業の多くが「失敗だった」と感じ、最終的には新たに別の.comドメインを取得**するケースもあります。
このような状況からも、.comドメインを取得する重要性が非常に高いことがわかります。
既に希望する.comドメインが取得されている場合でも、アメリカ市場では多少長いドメインであっても会社名やブランド名がそのまま綴られている方が覚えてもらいやすい傾向があります。そのため、長いブランド名をあえて短縮せずに使用している企業も増えています。
日本企業では、主に.co.jpや.jpのドメインが主流ですが、現在では日本企業も**.comドメインを取得することが可能**です。海外展開を見据え、特にブランド名に関しては、可能な限り.comドメインを取得することを強くお勧めします。

IPに注意する
ドメインを取得する際、既に存在する有名ブランドのネーミングに近いドメインを取得しようとすると、知的財産権の侵害に該当する可能性があります。
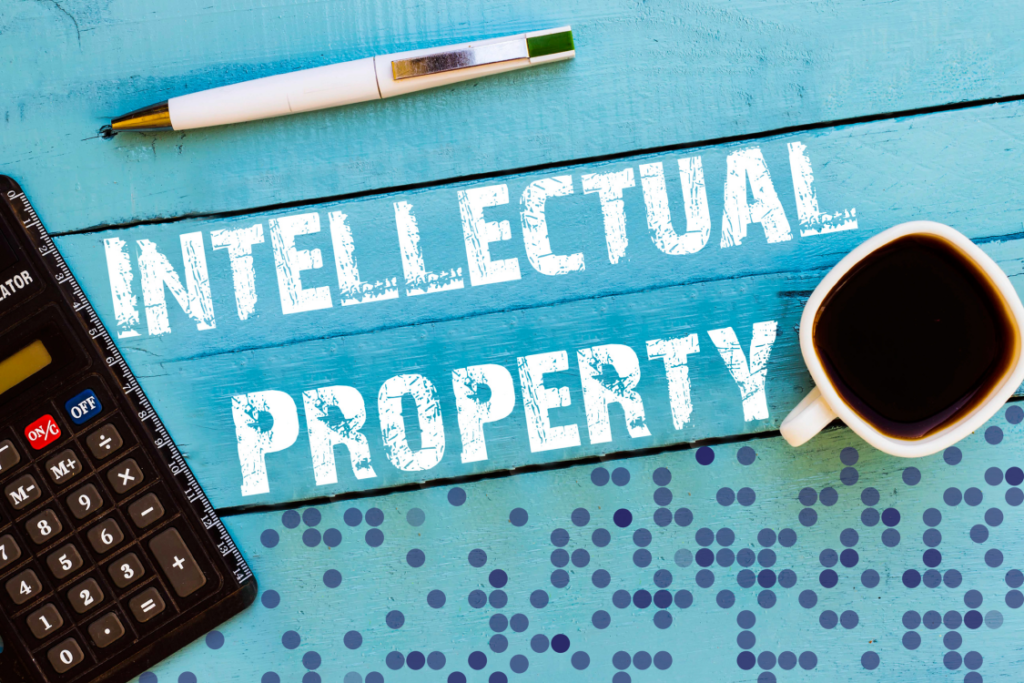
ここで、私自身の経験をもとにお話しします。
会社を設立して間もない頃、10年以上前のことですが、ドメインのIP侵害に関してある企業の弁護士から手紙を受け取ったことがありました。
当時、思い出の写真を木材に特殊加工で印刷し、壁に飾るプラークやコースター(壁掛け用のボード)を作成するサービスを提供していました。そのサービス名を「アートフォーメモリーzズ(Art for Memories)」とし、artformemories.comというドメインを取得して運営していました。
また、ドメインを取得する際、将来的に使うかもしれない別のサービス名として、**ライフタッチメモリーズ(Lifetouchmemories.com)**というドメインも候補として念のため取得していました。ただし、このドメインは取得しただけで実際には使用していませんでした。
しかしある日、**Lifetouch(ライフタッチ)**という企業から手紙が届きました。この企業は、主に学校の生徒写真を撮影するサービスを提供しており、「Lifetouchmemories.com」というドメイン名が自社の知的財産権を侵害しているとの主張でした。
Lifetouchmemories.comの使用はLifetouchの会社の知的財産権の侵害に当たると。Lifetouchmemories.comをLife Touchに引き渡してくださいというものでした。侵害しているから罰金というわけではなかったのですが、当時、自分一人の会社で顧問弁護士もなく、こういった手紙を受け取ったこと自体で怖くなり、直ぐにlifetouchmemories.comのドメインを先方に無償提供しました。もともとこのドメインは取得していただけで使用しておらず、損害賠償などもなくことなくを得ましたが、そこではじめて、このドメインがいいなと思って取得したドメインが知的財産権の侵害になることもあるのだ、と知ることになりました。
.jpなど、日本国内での販売であれば問題がない場合でも、.comドメインになると世界中から情報を閲覧されやすくなります。そのため、アメリカ市場で展開する際には、既にアメリカで使用されているネーミングや類似した名前が存在しないか、ドメイン取得の際にIP(知的財産権)を念入りに調査することが重要です。
現在、新たに海外展開を検討中の中小雑貨事業者の皆さま、または既に海外展開を進めているものの、うまくいっていないと感じる事業者の皆さまへ。今一度、現在の社名やブランド名について、以下の点を確認してみてはいかがでしょうか:
- 海外市場でどう受け取られるか
- 分かりやすく、覚えやすいか
- 発音しやすいか
- 発音した際の意味に問題はないか
- ドメインが取得できるか
- 知的財産権に問題がないか
これらをチェックすることで、海外展開の成功に一歩近づくことができるでしょう。
次回は、海外展開におけるネーミングについて、事例をもとにさらに深掘りしてお話しします。お楽しみに!